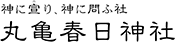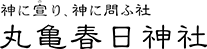「土用の丑の日」を広めたのは誰?発明神社と平賀源内の知恵にふれる夏|御朱印もご紹介

「土用の丑の日」といえば、うなぎを食べて夏バテ予防というイメージが定着しています。
しかしこの風習、江戸時代に平賀源内が仕掛けたアイデアだったことをご存じでしょうか。
香川県丸亀市の発明神社は、平賀源内を含む発明家22名を祀る末社で、彼の先見の明と創意を祈る人々に親しまれています。
今回は、「土用の丑の日」をテーマに平賀源内をひも解きながら、発明神社の代表的な切り絵御朱印をご案内します。
土用の丑の日とは?その“仕掛け人”は平賀源内
「土用」とは、五行思想における季節の変わり目のことで、夏の土用は特に暑さのピークを迎える時期です。
2025年の土用の丑の日は7月24日と8月5日。この日に「う」のつくものを食べるとよいという風習があり、うなぎが特に好まれてきました。
この風習の背景には、平賀源内の発想があります。
「夏にうなぎが売れない」と悩む店主に対し、「本日 土用丑の日」と書いた張り紙を勧めたのが始まりとされます。
いまでいうコピーライティングと販促を駆使し、需要を生み出した江戸のアイデアマンだったのです。
発明神社とは──創造と挑戦のご神徳
丸亀春日神社の境内社「発明神社」では、平賀源内をはじめとする日本の偉大な発明家たち22柱を御祭神として祀っています。
新しい発想を求める人々や、創造的な挑戦に向かう方々に信仰されています。
ご神徳の例
-
アイデアや企画が思いつかないとき
-
創作活動やビジネスの成功祈願
-
試験や発表に向けて集中力を高めたいとき
発明神社の静かな境内で、源内の功績に思いを馳せることで、新たな着想を得られるかもしれません。
発明神社の切り絵御朱印
発明神社では、常時2種類の切り絵御朱印が頒布されています。どちらも繊細な切り絵技術とデザイン性が高く、多くの参拝者に人気です。
聖徳太子 切り絵御朱印(第一弾)
発明の日(4月18日)にあわせて頒布が始まった御朱印で、曲尺や虎、十字架、手裏剣など多様なモチーフが盛り込まれています。
「日本最古の発明家」としての聖徳太子の功績に光を当てたデザインで、謎解き的な楽しさも魅力です。
平賀源内 切り絵御朱印(第二弾)
2025年5月から頒布されている御朱印で、エレキテルや磁針器、破魔矢、そして土用の丑の日にちなんだ図柄など、源内の多彩な業績が繊細な切り絵で表現されています。
構図の美しさとアイデア性が融合した一枚です。
授与情報
-
各種 初穂料:1,500円
-
授与場所:丸亀春日神社 社務所
-
授与時間:10:00〜14:00(郵送頒布も対応)
-
通年授与で、期間限定ではありません。
まとめ:発明家の知恵が宿る一枚を
平賀源内による創意と発信の力は、現代の私たちにも大きなヒントを与えてくれます。
「土用の丑の日」にうなぎを食べるという習慣すら、誰かのひらめきがきっかけだった――。
そう思うと、身の回りの何気ないことにも、発想を変える種が潜んでいるかもしれません。
この夏、発明神社で御朱印をいただき、源内の知恵にあやかって「ひらめき」と「挑戦」の祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。