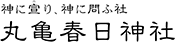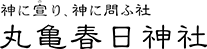空に夢を託した神 ― 発明神社に祀られる二宮忠八の物語

香川県丸亀市に鎮座する丸亀春日神社。その境内に、未来への祈りがこもった小さな社があります。
それが発明神社。日本の発明を支えた22名の偉人が御祭神として祀られており、知恵と創造の象徴として多くの参拝者を迎えています。
その中の一柱が、日本の航空の先駆者として知られる二宮忠八(にのみや ちゅうはち)です。
彼の生涯は、「人は空を飛べる」と信じ、困難の中でも挑戦を続けた発明精神そのものといえるでしょう。
二宮忠八とは ― 日本のライト兄弟より早く飛ぼうとした人
二宮忠八(1866〜1936)は、愛媛県出身の陸軍衛生兵でした。
ある日、カラスの滑空する姿に感銘を受け、「人も空を飛べるはずだ」と考え、自作の模型飛行機を製作します。
彼が作った「カラス型飛行器」は1891年に飛行に成功したとされており、これはライト兄弟の初飛行より12年も早い出来事です。
その後、有人飛行機の設計にも取り組みましたが、当時の社会に受け入れられず、資金面の限界などから開発を断念しました。
それでも彼の挑戦は、後の日本航空史において重要な礎となり、「日本航空の父」として高く評価されています。
発明神社に祀られる理由
発明神社では、創造力と努力によって人類の進歩に貢献した偉人たちが御祭神とされています。
二宮忠八は、「空を飛ぶ」という夢を、自らの観察と工夫によって実現に近づけた人物です。
彼は理解されなくても挑戦をやめず、後年には自ら飛行神社を建立して、飛行安全と未来の挑戦者たちへの祈りを込めました。
その姿勢は、現代にも通じる「信じて進む力」として、多くの人に勇気を与えてくれます。
切り絵御朱印で広がる発明の世界
発明神社では、聖徳太子や平賀源内をモチーフとした美しい切り絵御朱印が授与されています。
それぞれの発明や功績を象徴するデザインが施されており、知と技術への尊敬が込められた一枚です。
御朱印を通じて、発明家たちの精神に触れ、未来へのインスピレーションを感じることができます。
参拝の記念としてだけでなく、心に残る“祈りのかたち”として、訪れる方々に親しまれています。
空を見上げて歩む力を
ドローンや宇宙開発、空飛ぶクルマなど、現代でも人々は空に憧れ、挑戦し続けています。
二宮忠八の人生は、過去の出来事ではなく、今を生きる私たちにも通じる“夢を追いかける姿”です。
丸亀を訪れた際には、発明神社に立ち寄り、空を見上げてみてください。
きっと、あなた自身の中にもある飛翔への思いに、そっと火を灯してくれることでしょう。