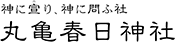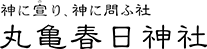江戸の驚異、エレキテル再現の謎 ― 平賀源内と電気の物語
「ビリビリする」「火花が散る」――現代人にとっては当たり前になった“電気”も、江戸時代の人々にとってはまさに“不可思議な現象”でした。そんな未知なる力に挑み、日本で初めて「電気」を庶民に体験させた人物がいます。そう、**平賀源内(ひらが げんない)**です。
今回は、彼の代表的業績とも言える**「エレキテル」再現の謎**に迫りながら、当時の電気知識や人々の驚き、そして香川県・丸亀春日神社に残る“源内の足跡”にも触れてみたいと思います。
◆ エレキテルとは何か?
「エレキテル(エレキテール)」とは、静電気を発生させる装置、つまり現在でいう「摩擦式の静電発電機」です。18世紀のヨーロッパで生まれ、医療や実験で用いられていたこの装置が、やがて日本にも渡来します。
源内はこの壊れたオランダ製エレキテルを見て、その機構を理解し、修理・復元し、さらには独自に再現することに成功したと伝えられています。
それは、ガラス円筒を回転させて摩擦電気を生み、電気火花を発し、人が触れるとビリビリ感じるという驚異の機械でした。
◆ 再現は奇跡か?源内の科学力
ここで大きな疑問が浮かびます。なぜ、壊れた洋式エレキテルを見ただけで、源内は復元できたのでしょうか?
◉ 蘭学の知識と国際感覚
源内は長崎を通じて蘭学(オランダ語による西洋学問)を学び、西洋の科学技術にも深い興味を持っていました。実際にオランダ語文献や図解を読み、仲間の蘭学者と協力しながら、機構の全体像を把握したと考えられています。
◉ 手を動かす発明家の感性
源内は頭で考えるだけでなく、実際に自分で実験・製作を行う“実践派”でした。彼が手がけた様々な工芸や機械技術からも、その高い創造力と観察眼が伺えます。
◉ 和製エレキテルの独自性
源内が作ったエレキテルには、日本の技術――例えば漆器や木工、和紙などが用いられ、まさに**「和製エレキテル」**としての魅力を放っていました。
◆ 江戸の人々と“ビリビリの驚き”
平賀源内はこの装置を「見世物」として各地で披露し、江戸の町民から大名にいたるまで、大きな話題となりました。
火花を散らし、体に衝撃を与えるこの装置は、当時の人々にとって「雷」や「神の力」にも近いものとして受け止められ、驚きと神秘をもって語られました。
中には「これは病気を治す霊力がある」と信じる人もいたほどで、エレキテルは科学と信仰が入り混じった象徴的な存在でもあったのです。
◆ “電気”という未知と、信仰の交差
現代では科学と信仰は別物のように考えられがちですが、江戸時代の人々にとって「電気のような不思議な力」は、しばしば神や霊と結びつけて理解されていました。
雷神=タケミカヅチ、天照大御神の光、陰陽五行――そうした思想の中で、平賀源内がもたらした「電気の力」は、人智を超えた“何か”として深く受け入れられていったのです。

◆ 丸亀と平賀源内、そして今に伝わる御朱印
そんな天才・平賀源内は、香川県讃岐国(現・さぬき市志度)出身であり、四国に数々の足跡を残しています。丸亀市の丸亀春日神社は、そのゆかりの地の一つ。古来より学問・知恵・文化の神を祀るこの神社の末社に、現代的なユニークさと歴史的深みを併せ持つお社があります。
その名も――
🔧 発明神社(はつめいじんじゃ)
この発明神社は、平賀源内をはじめとする日本の発明・創造の歴史を支えた偉人たちを祀る神社であり、まさに“知恵とひらめきの源”とされる場所です。
そこでは、平賀源内にちなんだ御朱印が授与されています。
特に人気なのが、
✨ 「平賀源内 切り絵御朱印」 ✨
エレキテルを象った美しい切り絵が施されたこの御朱印は、源内の知的好奇心や発明の精神を今に伝えるアート作品とも言えるもの。手に取った瞬間、江戸時代の科学者たちが胸に抱いていた“まだ見ぬ世界への憧れ”がよみがえってくるようです。
◆ おわりに ― 源内の好奇心を、いま感じて
平賀源内が再現したエレキテルは、当時の常識を超える“驚き”と“知の挑戦”の象徴でした。そしてその精神は、今もなお発明神社に息づいています。
「ひらめきがほしい」「アイデアに行き詰まっている」「創造的な力を高めたい」――
そんな思いを胸に、ぜひ丸亀春日神社・発明神社を訪れてみてください。
切り絵御朱印に込められた知恵の神々しさが、きっとあなたの背中をそっと押してくれるはずです。